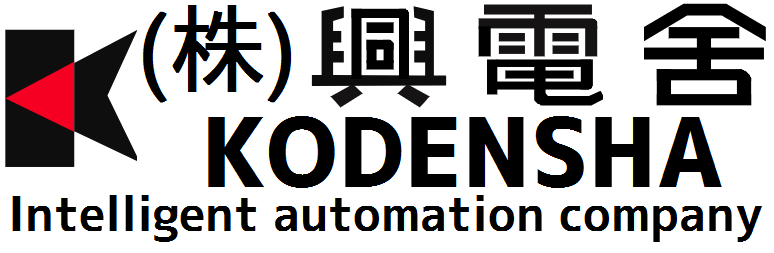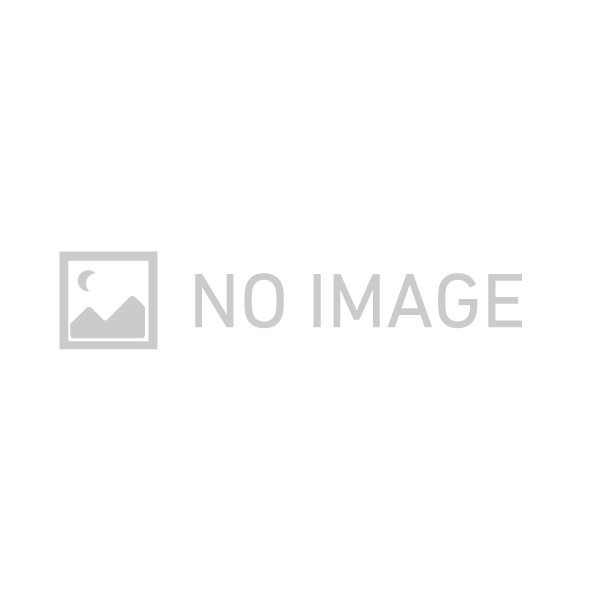M社長の想い出
先に書いたスコラ・コンサルトの経営者アカデミーというワークショップにはこんな思い出もある。当時私は30代であったが、同じ参加者にたしか還暦すぎたばかりの大手企業子会社のM社長と、いわゆる「参謀役」のNさんがおられた。コンクリート製品を主力にする同社は、当時親会社から受注が設備投資の一巡で激減したため、リストラを含む赤字からの抜本的立て直しの最中であった。私自身は社内の世代交代の難しさがどうにもならず、思いああって参加したのだが、オーナー中小とはことなる、大企業の子会社の難しさというものをそこで改めて知ったものだ。
当時のMさんの会社の変革ストーリーは、スコラ・コンサルトの遠藤PDが「衰退産業 崖っぷち会社の起死回生」という書籍にまとめられ、そこには経営者アカデミーのエピソードもでてくる。年末になって改めて読み返しているのだが、当時がよみがえる。
そのときのスコラのやり方は独特であった。経営者同士が自分のおかれた境遇などを披露していく場面などでは、経営としてなじみのない弱みを見せることに、抵抗感を示す参加者もいたものだ。そして、スポンサーシップ、コア・ネットワーク、参謀機能といったスコラ的アプローチの概念の理解が促される。たとえば参謀機能とは、戦略論にある「経営参謀」とはかなり意味合いが異なる。これは忖度と腰巾着といった言葉にみられる、上司の前では調子のよいことを言いながら、陰で悪口を言っているような人物像とは真逆のスタイルを差す。つまり会議や現場などの公の場では上司に対して公然と厳しい指摘をしながらも、上司のいない場面では、その考えをメンバーにわかりやすく翻訳していくという役割だという。同社のN役員をはじめとした改革の世話人の方々が、同時進行のスコラのサポートの元、この機能を果たすべく格闘をしておられたのも、同社を九州に訪ねたときの懐かしい思いでである。
特に議論の渦中で社長にもズバリと切り込んでいくN役員のキャラクターは強烈で、おっかないような印象まであった(ごめんなさい)。M社長はそんなN役員を我々に「カウンターパートナー」と常々紹介されていた。M社長のそうした厳しいメンバーをパートナーとしてとらえていることに、人としての成熟と互いの信頼関係の深さというものを感じたものだった。
またアカデミーの中では、独自の「経営の軸」となるものを作りあげることに毎回向き合うこととなった。私は、ある社員さんから発案された「流れるようなものづくり」としたのだが、それ以上の市場につながるような言葉を生み出せず、その行き詰まりにしんどい思いもした。
そんな中、M社長が打ち出した「売上100億」には、正直唐突感と論理の欠如を感じたものだ。しかし今となってはその言葉の裏にある「本気の想い」こそが改革の原動力だったことがわかる。さらに2年に及ぶワークショップの終盤で見いだされた「鉄に勝つ」というコンセプトには新市場開拓への念いが秘められており、それこそが奇跡の回復を遂げるにいたった源泉になったことをほんとうの意味で理解したのは、アカデミーが終了し、書籍が出版されるころのことであったように思う。
顧客価値という論理を考えつつ、一方で人間の弱さや悔しさといった感情にもふれていく場は当時の自分の経営観の基盤をつくってくれたように思う。そしてM社長の言葉を私が唐突感をもってうけとったように、こうしたトップの打ち出すテーマの背景というものを他者が理解するには「問い返し」を含めた深い対話の時間が必要であることもこの場で学んだように思う。
今では心理的安全性という言葉がこれほどまでにポピュラーになることに驚きも感じるほど、自律型組織開発はよく知られたアプローチとなった。そんななかスコラのアプローチはボトムアップ的なものとして誤解されることもあるが、この経営者アカデミーでは、自律性を高める環境には、ほんとうの意味での強いリーダーシップが不可欠であることを示していた。今私自身愕然とするのは、当時のM社長に近い年齢になってきたということと同時に、当時追求していた「軸」というものに、どれだけたどりつけるようになったのだろうか、ということだ。
M社長の会社のみならず当社にも支援していただいた遠藤PDにその昔支援の要諦を聴いたことがある。いわく「その会社にほんとうによくなってもらいたい、と思いながら関わっていくと、だんだんよくなっていくのよ」といった内容だったと記憶している。およそコンサルタントという、具体論を教える立場からは普通は聞こえてこないような響きがある。しかし人間の織りなす組織は、こうした想いの重なりがあれば、時間はかかっても、持続的な変化を起こしていくものだということを身をもって体験されているからこその言葉として受け止めた。
実は私自身、数年前にあることがきっかけでそれまで繰り返し手にしてきたこうしたスコラ式風土改革に関する書籍をすべて処分してしまった。とりあげた本書は最近中古で買い直したものだが、そのことに触れるにはもう少し時間が必要となりそうだ。