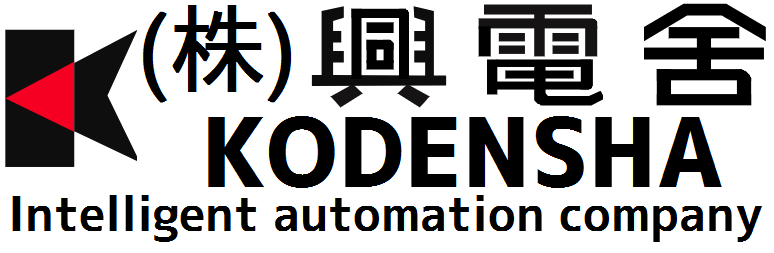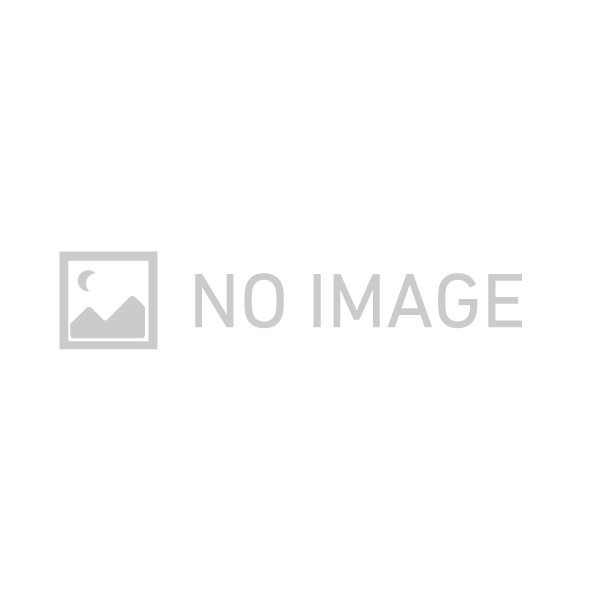コロナ禍で変わるもの
コロナでいろいろな事が変わった。たとえば葬儀に行く回数もめっきり減ったし、結婚式も身内であげることが多くなったようだ。
その昔、よく社員さんの結婚式にお呼ばれしたが、30歳そこそこで仲人をやったときには、それこそ緊張した。そうした立場になると思ってもみなかった妻は「黒留袖なんてつかわないと思ったけれど、まさか役に立つなんて」と言ったものだ。その留めそでも、いまでは箪笥の肥しになって久しい。
特に結婚式に呼ばれるときには、社員さんの家族の方と直接接することになるので、私にとっては、なんだか「新たな家族の生活を支えなければ」というプレッシャーがかかる場でもあった。スピーチの挨拶も、気の利いた話せるわけでもなく「新たな気持ちで経営に励みます」的な内容をいつも繰り返したものだ。
そういう自分自身の結婚式は、今思えばまだ当社には入る心構えがなかった時期だった。とはいえ社員さんをはじめ、父の案内でお客様の社長さんや経営幹部の方にも来賓にお越しいただき、知らない人の前で人形のようにさらされるなあ、と緊張しつづけた。また、父の葬儀も、肉親の死を悲しむゆとりもなく、取引先様にひたすらあいさつを繰り返した、暑い夏だったことだけが記憶にある。
その意味では、こうした儀式がコロナでプライベート化することによる、若干の気楽さもある。一方で昭和的な仕事と家庭の一体感が日本のある時代の強さの源泉であったともいえるだろう。JOB型というものも進む中、ドライな関係性の中で、どうやってつながりを見つけていけばよいのか、という戸惑いもある。
そうした中、たまたま、NHKの「サラメシ」という会社でのお昼ご飯にフォーカスを当てた番組で、帝国ホテルの社食が、ホテルのシェフによって運営されるようになったことを紹介していた。こちらもコロナで宴会需要が減少する中、社員の雇用を守るために、今まで外部の業者に依頼していた社員食堂をホテルの宴会担当のシェフが取り仕切ることになったという。
価格を抑えるために、しいたけのいしづきなど、宴会ででるあまり材料を使いながら、長年のキャリアを土台にして、味で勝負する。そして、社員からは「シェフの味に毎日接することができる」という喜びの声があがる。
番組にはではでてこないが、パーティーのような華やかな仕事が、社員食堂となることには、複雑な心境もあったのではないだろうか。しかし、「ほかにできることもないし」と、淡々と取り組むシェフの姿に、こちらも一線に出ることを期待して入社してきた若手も、シェフの技を身近で盗む機会ととらえ、独自のアイデアをして、バックヤードで働く社員に活力をあたえようと創意工夫をする。そうした中にプロとしてのさわやかな矜持というものを感じ、10分程度の映像であったが、心に暖かなものが残った。
生きていく中では、どうしても避けがたい不都合な現実というものが起こる。コロナ禍もまさにそうしたものの一つであった。しかし、人間は不都合の現実からしか変われないということもまた真実であろう。最近の若い方は、地球環境問題や、自死の減少といったような、表面的な資本主義における成果を超えた、より人として根源的なものに、自分事としてのやりがいを見出すようになってきていると聞く。
私自身も、目先の成果にあくせくしては、日々もがいているというのが現実だが、それでもより根源的な社会のための仕事というものを追求していきたいと、この短い映像から感じた。なんか良さげなこといって終わったが、たまにはよしとしよう。これもコロナでの変化だ。