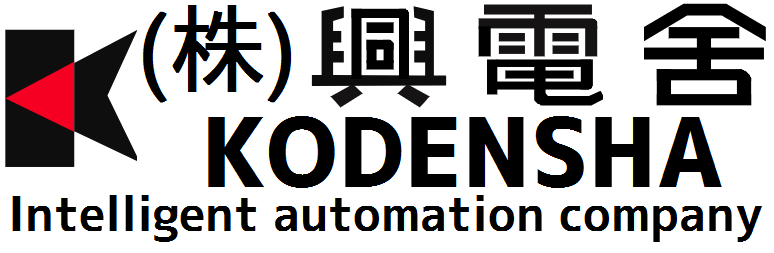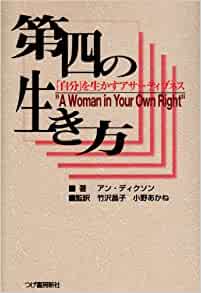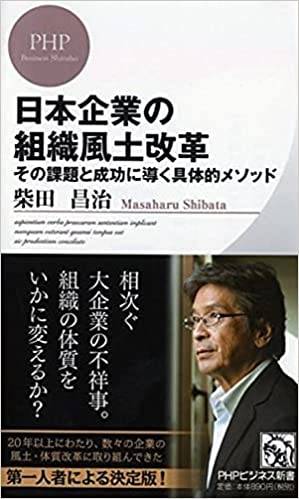アサーティブネス(3)
人間というものは恐ろしいもので、感情を押し殺していると、本当に自分が何を感じているかがわからなくなってくるものです。私自身、父の喪失の悲しみをわずかに感じられるようになったのは、父が逝ってから10年以上もたった後でした。その当時は自覚的ではなかったのですが、悲しみの感情を押し殺していると、喜びや楽しみといったものにも無感覚になっていってしまうということも体験しました。
そもそも感情とはなにか、ということへの手がかりになったのは、20年前に始めたマインドフルネスの瞑想(ヴィパッサナー)と、その後であったマーシャルローゼンバーグのNVC(非暴力コミュニケーション)というう考え方でした。詳細はまた機会があれば触れたいと思いますが、人間が古い脳のはたらきとして、身体の感覚の変化や違和感というものを、新しい脳が悲しい、うれしい、こまっているという風に感情というある種の概念として認識する間には、ある程度のギャップがあり、トレーニングが必要ということです。赤ん坊はミルクがほしいときには泣き出しますが、「おなかがすいてこまっている」という言葉にはできません。
職場でも、「相手が感情的になるのがいやなので、直接言うのはやめよう」という話をしばしば聞くこともあります。感情的になるのはむしろ普段から「感情を押さえて、ないものにしている」結果のような気まします。ポジティブシンキングなどもはやっていますが、こまったときには「こまった」、しんどいときには「しんどい」と言葉にできることが、人間の本来の姿に近いの出はないかと思うのです。
そして、それでも自分は何をなしとげたいのか、という本来の意図に常にもどれること。そうした一人一人へのエンパワーメントが、実は組織の立場や役割を越えた、真の人間の力が発揮される場になるとおもうのです。
ネルソンマンデラ首相はその就任演説で M.ウィリアムソンの一説「私たちが恐れていることは、私たちが無力であるということではなく、私たちが計り知れないほどの力をもった存在であるということである」をとりあげていて、これは私たちがとても勇気づけれる言葉です。相手のことを尊重しつつ、自分のなしとげたいことを実現するための、アン・ディクソン氏のいう「内面の力」。これは地位や役職をとびこえて、一人一人が対等に持っている「力」でもあります。そうした力がより人間の本性にしたがって発揮されるような組織体をめざし、アサーティブの学びというものはこれからも少しく続けていこうと思っています。