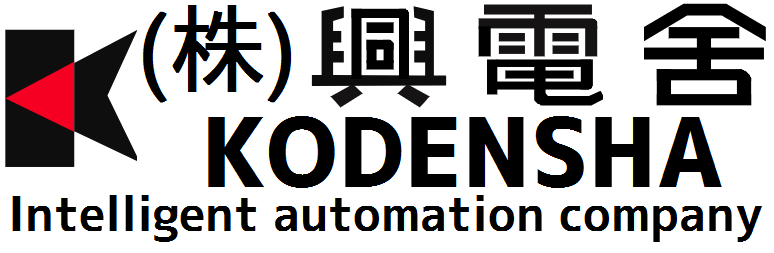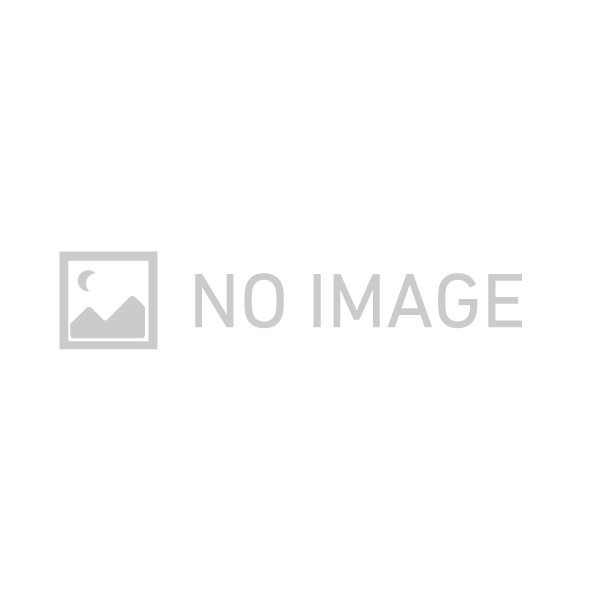書籍の紹介「夢を叶えるために脳はある」池谷祐二著
脳科学者池谷氏の、高校生との授業をもとにした3回シリーズの最終講義と銘打った15年ぶりのシリーズ
最終章である。その導入は哲学、現象学的な認識論からはじまり、さらに人間らしさとは、そして生命とは
何か、を数々の科学的論証から導いていく、大変スリリングな展開の著作である。
2007年にブルーバックスで「進化しすぎた脳」を手にしたときの、ある種の衝撃は多くの人が感じた
であろう。そして脳科学の池谷先生の名前は一躍多くの人にしられることになった。しかし、その後の著作
も含め、同じ言説を広めるのではなく、研究者として新たな探求をしつづけている著者の姿勢にも感銘を
うける。今回は同じ講談社でも分量の面でも、領域の面でもブルーバックスには入りきらないため、単著の
形式をとったのではないかと拝察されるが、とても3日の講義とは思えない緻密な構成にうなる。
授業形式という意味では、加藤陽子氏の「日本人は「戦争」を選んだ」シリーズも思い出すが、難解になり
そうなテーマが実際の授業という形式にしているため、頑張ってついて行こうという気持ちにもなる。
とはいえ、いわゆるお手軽な対談本とは対極の作りで、この授業のために15年間準備してきたと言わん
ばかりの重奏な構成に筆者の科学者、教育者としての執念を感じる。加藤氏も小林秀雄賞を受賞しているが、
本書も同じ賞を受賞したことを知った。小林賞はその多くが人文系の著作が中心と思われるが、本書は科学
視点でありながらも、その問いかけは哲学や宗教領域にも広がる、文理横断的な色彩をもつ。
たしかに第一弾の当時はディープラーニングの技術がまだ脚光を浴びる前であり、人工知能の深化が、脳と
は何か、という話の壮大な補助線になっているところが大変興味深い。。たまたまこの数ヶ月ディープ
ラーニングE資格の取得のために、AI分野を少しく学習してきたが、人工知能の工学的解説では、人間の神経
細胞を模しているとはいえ同じ物ではないという説明が一般的かと思われる。しかし著者は、研究でも人工
知能を活用しているからか、逆に積極的に人間の脳と人工知能の類似点を上げ、そこから脳の特有性を
説いている。
すなわち、コンピュータが学ぶがごとく、脳そのものはあくままでも単なる電気信号の入力(=
ナトリウムイオンのチャネルへの出入り)という化学現象に対して、教師あり学習におけるアノテーション
(ラベルづけ)をおこなっているにすぎず、客観的外界的状況がわかっているとはいえないものである、
ということをさまざまな脳科学の実験の例を提示することで示している。
例えばゴムの手をたたく動作と同期して、脳に電気信号を与えると、人間はその手を自分の手と認識
していくというから、心理学的なエゴ概念は脳でつくられている幻想にすぎず、仏教の無我論にも
つながるような話である。まさに映画のマトリックスの構想は、現代の脳科学からも導き出されると
いっているようだ。
ちなみにディープラーニングにおける非線形関数であるシグモイド関数の動きが、マウスの腸の
伸び縮みと同じだという事を利用して、動物の腸からディープラーニングの回路を実際につくって
画像認識までさせてしまう、という実験を試みた、という話には驚かされる。がこうした実験をやって
みようと思う著者の科学者としての探究心にも圧倒される。また、人間の網膜の限界の話から、マゼンダと
バイオレットは同じ紫でも違う物だと言うこともはじめて知った。
本書ではさらに熱力学のエントロピー増大則とビッグバンから、プリコジンの散逸構造論にまで踏み込み、
人間が存在する意味、目的にまで言及が及ぶところは壮大だが、こうして脳を超えて、科学とはなにか、
生命とはなにかという問いにまで到達する展開には、今までの常識を揺さぶられる快感がある。
結局科学というものは、自然現象を人間の脳が理解できる様に整理、翻訳しているものであり、この解釈性
が解釈不要のシミュレーション可能な人工知能との最大の違いというように受け取ったが、そう考えると
科学は結局限界のある脳というものへの解釈づけである言うことが腑に落ちる。すると客観性をもつ科学
というものが、ある種の物語のようにも思えてくる。トーマス・クーンのパラダイム論を持ち出すまでも
なく、そうした脳の限界があるからこそ逆に科学というものが体系づけられる、探求の価値があるという
新たな視点がえられた様にも思う。
幾重にも伏線の重なった本書は、ネタバレしそうな推理小説のような側面もあり、内容に触れるのはこの
くらいにしておくが、昨今のLLMの発展も含め人工知能が当たり前の時代になってきたからこそ脳をしる
ということの奥深さを強烈に印象づけてくれる一冊であった。ちなみに「夢を叶える」という魅惑的なタイトルにも惹かれたが、これも良い意味で予想を裏切られるのも、本書の一興でもある。