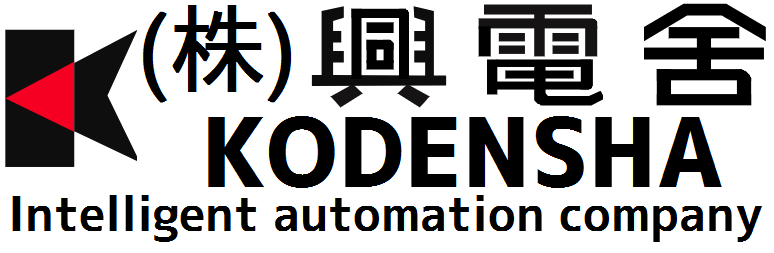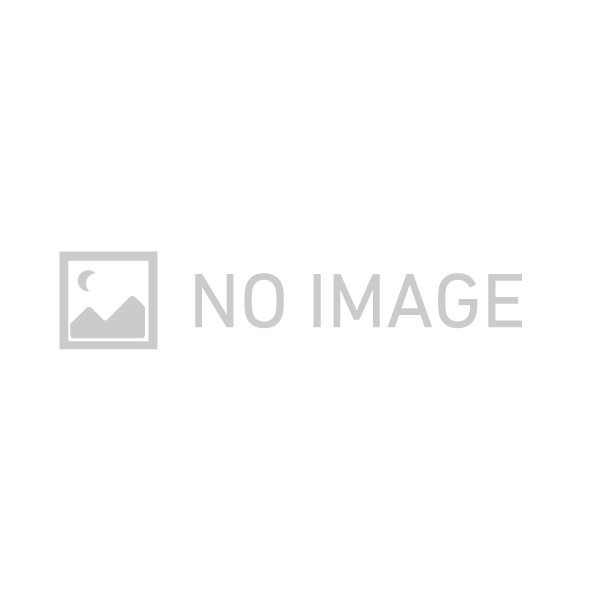良い季節になって
過ごしやすい季節になり、またコロナの収束もともなって外に出ることの心地よい季節になってきた。
連休を前にして、最近行ってきた美術館や博物館の展示の様子を紹介してみたい。
まず大所(おおどころ)では、国立新美術館で開催されている、「ルーブル美術館 愛を描く」という企画展である。国立新美術館では、以前「葛飾北斎」のときに入場に1時間以上もかかった記憶があったので、やや警戒した。しかし今回は、コロナの影響だとおもうが、時間ごとの前売り券制度も導入されたこともあり、10分ほどの待ち時間で会場に入れた。しかし、一歩会場に入ると大勢の来場者で相当の混雑をしており、なかなか絵に近づけないほどの盛況ぶりであった。
今回はルーブル美術館に収蔵されてる作品の中で、愛、すなわち人間の情欲に関係する作品を時代をこえて集めたという点がユニークである。色調も明るくファンタジックな神話の世界の描写から始まり、落ち着いたトーンに変わるキリスト教の倫理観に基づく画風への変化、さらには中世から近代へと時代が進むと、性的な暗喩がふえていく世俗的な描写へと、まるで成人発達理論での人類の進化のプロセスを、愛という視点から追っていくような感覚を覚える。こうしたテーマ設定がなりたつことそのものが、収蔵物の豊富なルーブル美術館の真骨頂なのだろう。また、こうした作品のプロットが、音楽家や舞踏家の手によってオペラやバレエなどの作品として今日まで伝えられている点も、歴史の重みとしてあらためて感じられた。
会場には、題名に引かれてか、カップルの方、女性の方がわりと多く私のようなロートルに足を突っ込んだ人は少数派だったか。(別にそれでなにというわけではないのだが)、そうした光景に自分自身若き日のノスタルジーを感じるのは自意識過剰というものだろうか。いずれにせよ、学芸員の苦労が忍ばれる、こうした抽象的なテーマを切り口の展示はあまりないと思われ、一見の価値はあると思う。
もう一つ、上野の国立博物館で行われている、東福寺展にも行ってきた。こちらは、ルーブルほど混雑はしていなかったが、連休までの開催なのでゴールデンウィークでの若干の混雑は予測される。
東福寺で有名なのは、紅葉の景色が見事な回廊であったり、南円堂の国宝四天王立像であったりする(そして、そうしたものも取り上げられている)が、今回の展示では、吉山明兆という画を極めた僧侶がその生涯を、東福寺にまつわる芸術にささげたという事実を大きく取り上げており、大変興味深かった。中でも圧巻が、明兆が3年余の歳月をかけて完成させた五百羅漢図である。全50幅のうち現存する47幅が、一昨年までなんと14数年かけて、それこそ手作業で修復されたという、その事実もまた驚きである。
羅漢とは、仏教の悟りを開いた者として、預流果、一来果といった修行者より高い位の尊敬を込めた言葉とされるが、実際の描写は、ひげを剃ったり、目薬をいれたりと極めて人間くさいものであり、この対比がまた面白い。羅漢像といえば、地元川越の喜多院という寺院のユーモラスな石仏群も有名であるが、とかくシリアスな仏教芸術の中でこうした庶民的な画をみると、悟りはまさに日常にあると感じる。
実は吉兆自身も、羅漢図を描くことで親の死に目に会えなかったというほどであり、自身も僧侶ではあったものの、座禅よりこうした日常の仕事の中に仏道の修行をみたのではないだろうか。私自身も羅漢のように、日々のプレッシャーやストレスの中にあっても、朗らかに仕事を取り組むということが在家としての習練であることを教えられているように思える。これ以外の明兆の作品も、一筆書のような大胆な水墨と、顔の描写に代表される精緻な筆遣いのコントラストが日本画の領域をこえており、その他の画も見応えがある。先に触れた四天王像をはじめとした彫刻作品も現物がかなりのスケールで会場にもちこまれており、こうした展示も含めて、京都の一寺院の魅力を余すところなく伝えていた。
少し面白く感じたのは、両展示とも、写真を撮って良いスペースをわずかながらもうけていることだ。多分インスタやSNSでの宣伝をねらってということだろうが、昔の感覚では撮影禁止か、場合によってはまるごとOKかという間隔だが、あえてそうした撮影スペースがつくられていることが時代の変化を感じる。
その他、マティス展(東京都美術館)やブルゴーニュ地方の特集(国立西洋美術館)など、コロナの収束とともにさまざまな展示が活発に行われるようになってきている。日々はなかなか汲々としてゆとりのもてる実感がすくないのが本音だが、コロナを通じて文化活動の停滞に直面をしたことを考えると、こうした場に足を運べる日常の復活を素直に喜びたい。