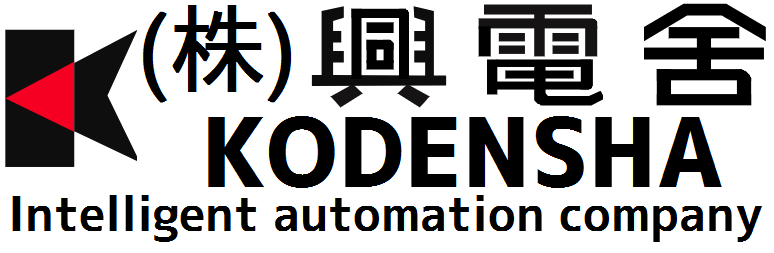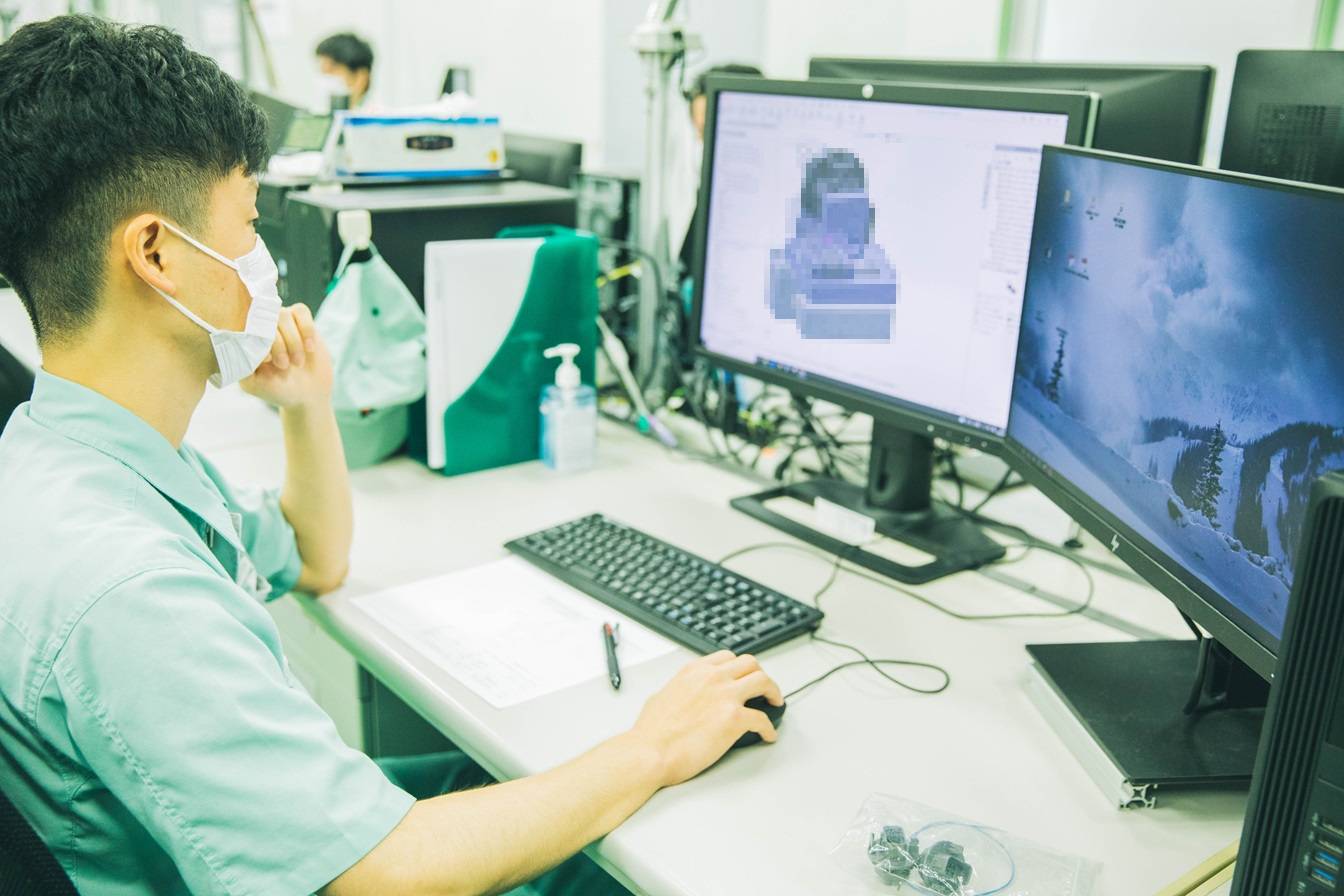田中一村という生き方
行列のできている上野の西洋美術館でのモネ展を横目に、どんづまりにある東京都美術館で
開催されている「田中一村展」に先日足を運んでみた。昨年は、他の美術館で江戸の伊藤若冲
との併設展も企画され、その華やかな色彩から人気が高まっている。一方その生き方への共感から、
近年では教科書にもとりあげられているらしいが、奄美大島に住んだ「日本のゴーギャン」程度の
予備知識しかないまま、それでも混雑している休日の会場についた。
まず感じたのは展示数の多さで、企画者の収集への本気度を感じる。その後NHKの日曜美術館で、
企画まで話が取り上げられていたが、新たな作品の発掘が続々続いているらしい。それも一般の
所有者から見つかるということで、まさに食うために描いてきた生前は無名の作家としての苦労が
忍ばれる。
入場すると最初に目にする、10代前半の作品群が、成人と見間違うような漢詩の入った南画の
数々であることにまず驚かされる。例えばジャズの演奏家には、家族の影響をうけた早熟な演奏家が
何人か挙げられるが、一村が東京芸大に入学しつつすぐに退学して、独自の道を選んだのも、こうした
実践型の職人気質も影響したのだろうか。
その性格からか、20代前半には自分が描きたい自然画を支援者が受け入れてくれず絶縁するとか、
中年期にはじめて公募の展覧会に入選するものの、翌年自分の自信作が入選しないことで主催者に
抗議して画壇の実力者との関係を絶ったりしていてなかなか気性の激しさを感じる。自分を認めない
世の中が問題だという姿勢は、世間ずれして生きにくいところもあっただろう。
それでも東京の画壇をみかえしてやろうという計画のもと、50代で奄美大島へ退路をたって転居をする。
その後の様子は、同じNHKの「(ピーター)バラカンが見た奄美大島」を後日ネット配信で知ったが、
こちらの番組も丁寧な取材がなされていて、なかなか見応えがあった。
そこでは奄美大島という南の孤島が、琉球、薩摩、米国と統治機構が変わるなか、厳しい生活環境を
くぐり抜けてきたこと、そして作品に取り上げラル南国のサテツといった植物が、観賞ではなく実は
命を繋ぐために食用として栽培されてきたことなどが、一村との関わりを通じて描かれていた。
氏が特産の大島紬の工房で染色工として生活をつなぎながら、こうした植物などを画題とした
ことには、単なる風景を残そうという以上のメッセージが感じられる。
「不喰芋(クワズイモ)と蘇鐵(ソテツ)」という作品では、クワズイモという南国植物の
つぼみから枯れるまでのサイクルが描かれ、死生観さえ表現しているとも言われるらしい。
氏は、作品はほめらえても、けなされてもかまわない、自分がつかみ取った物を残したまで
というようなことを書き残しているという。
そこには奄美に息づく大自然の神秘と雄大さ、人々の暮らしにふれ、いつしか反骨の情念を超えて、
本当に自分の描きたいものを描きたいように描くという、納得のできる作品作りへの転換が見て取れる。
展示の最後段にある作品には、それまでの数々の秀作の結晶としての重みを感じられる。
私自身、残りの人生がどのくらいかを意識する年齢になった。世の中は高齢でも現役で活躍
する人も増え、そうした期待とともに、ある種の諦念も感じるようになる。展覧会や番組で明確に
語られた訳ではないが、奄美に渡ってからの一村の価値観の変化が、生業の違いを超えて伝わってくる。
先のNHKのドキュメンタリーには、島の人の小さな遺影写真を、一緒の工房で働く人のために
(支援のための幾ばくかのお金をもらい)額縁大に書き変えるというエピソードがある。彼にとって
はこうした日常の画作と、上記のような作品の創作のどちらにも全力であたっていたように思われる。
そこには無名またよしとした彼なりの画家としての納得というものがあるのではないか。そして、結局は
自分自身の独自の道を歩むしかない、という厳然たる事実を伝えているようだ。
日曜美術館では、波乱の生涯が語られがちな一村の、作品を見てほしいというコメントもあったが、
やはりこの画家は生き方と作品が不可分であることを強く感じざるをえない。
展示会は今月(2024年11月)いっぱい続くようだ。そしていつか奄美で見てみたい。