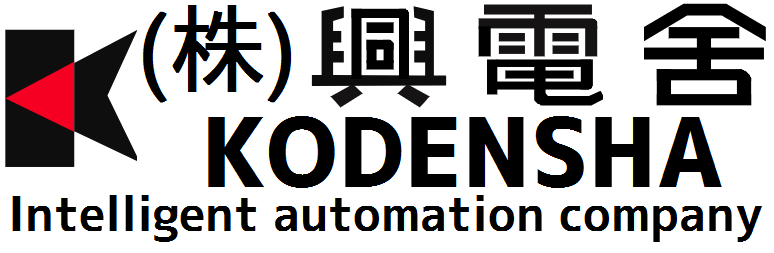母の思い出(3)
父が亡くなったときに、私が代表になることは当然のことと思われていた。今考えてみると、母も長年経営に
携わってきたので、中継ぎ的な対応もできたと思うが、母はなぜか徹底的に裏方に徹した。
30を超えたばかりの私にとって、小企業とはいえその重圧は重かった。それまでエンジニアだった自分にとって、
企業経営というものが果たしてなんなのかがイメージつかなかったのが本当のところだ。しいていえば、松の木に
首をくくって保険金で会社を救うのが仕事くらいに思い詰めていた。そして当時はなぜかそうしたニュースばかり
が眼に入った。
私のそうしたプレッシャーを母は知っていたとは思うのだがが、私のいないところで母は「あの人は10年は苦労するわよ」
といっていたという。「丸いものを四角にするには時間がかかるのよ」と直接いわれたこともある。母のそうした
突き放したような物言いに、腹が立つというより、なにか不思議な感じをずっと抱いていた。
急な跡継ぎという環境の変化で、着任早々に体調をくずし、山のような薬にお世話になったこともあった。それでも母は、
調子のわるい私を無理矢理にでも職場に引きずりだした。薬を飲むと一時的に元気はつらつになるが、仕事が終わると
燃え尽きて動けなくなるというようなことを繰り返したこともあって、そのときの身体の負担がこの年齢になって響いている。
仕事が出来るだけありがたいのではあるが、お酒も食事も自由にできない事は、自業自得といえ、自分の虚弱さを時折悔しく思う。
後継者の方で、父親との関係に悩むという話はよく耳にする。私の場合は、経営方針で母とぶつかることはなかったが、
完璧主義の母親に常に監視されているという感覚はあったかもしれない。風土改革を進めていったプロセスでは、「社員にそんなに
寄っていってはダメ」と一度だけいわれたこともある。当時はこの点について若干の反発はあったが、今となっては分かるところも
あるか、まだまだ試行錯誤がつづく。
母は裏方ではあった、がそれでも、裏方のオーナーだからこそのお金の使い方など、晩年になってわかってきて、自分がカタをつけた
と思ったことに母の関与があったことを知ることもあった。母も対外的にはお酒もたばこもやらずにいたが、自室では隠れるように
携帯型のポケット灰皿をつかって一服していたことを知ったときには少し驚いた。晩年には、小さなビール缶(今ではめにしなくなった)
を食事とともに飲み干して、ちゃぶ台の脇に横になり「今日も一日終わった」と確認するように言っていたことを思い出す。
そこには戦争、夫の急逝、子供の事故、そして経営でのさまざまなできごと、そうした幾多の出来事を乗り越えて、夢や希望ということ
はなく、とにかくその瞬間瞬間にやることをやって生きていくという、一種の達観を感じさせられたものだ。
母は父がなくなってから10余年の後に、自身もがんに罹患することになった。手術のあと、標準治療の抗がん剤を拒否して、病院と
またもめた。親戚総出でなんとか受け入れる病院をさがしたが、はじめて自分の意思を示したようにも思った。その後仕事をしながらも
民間療法に毎日かよっていたが、約一年後に再発してしまった。それでも、病院に入院する一日前まで、むくんだ身体でありながら、
自力で食事をとっていた。入院したその晩に吐血して逝ってしまった。間一髪だった。
がんになって母親からは、「あの人はよく頑張っているわよ」「いざとなったら会社はやめてもいいのだから、と言っておいて」と妻を通じて伝えてきた。それを聞いたとき、重くのしかかってきたものが少し緩んだような感覚をもった。それでも直接言われるのは、小言の方が
多かったように記憶してるが、その記憶も遠い。そして、闘病をしながら、遺産の処理だけでなく、自分の遺品を細々と整理し、
これは処分する、これは○○さんにあげるなど、事細かに整理した。見事な完璧主義だった。
母が亡くなった後、それでも残った遺品を整理していたら、パスポートがでてきた。父の手術後はそれでも国内旅行も一緒に行きだして
いたが、いつかは海外とおもっていたのだろう。遺品のパスポートは真っ白で一つの出国印もなかった。ゆとりをあたえられなかった
罪悪感も軽く感じつつ、父親共々、会社に寿命をささげたようにも思われた。
母の妹である叔母が数年前になくなったとき、息子であるいとこがこんなこことを言っていた。「母は専業主婦でしたが、それでも
いろいろな波風を乗り越えてきて、改めて壮絶な一生だったと思います」
他人にとっては、自分の母親の話など薬にもならないだろうし、マザコンと言われるかもしれない。
(まあ男はみんなそうだという開き直りもあるか。)それぞれの人にはそれぞれの固有の人生がある。私もあと十年ほどで、父や母が鬼籍に入った年齢になる。いろいろなことを乗り越えたようにも思うし、
なにもなしとげなかったようにも思う。それでも、母親と共に仕事をしてきたというのは、少し独特な
人生だったのかもしれない。そんなことに改めて気づいた。(この項了)