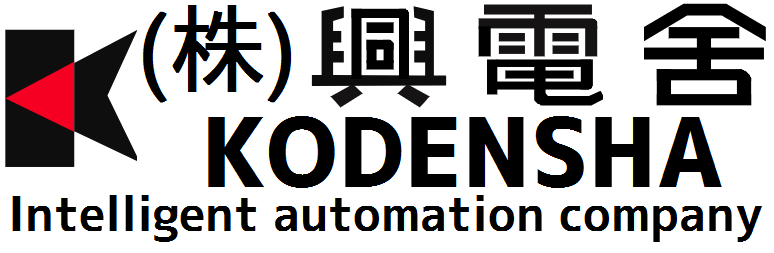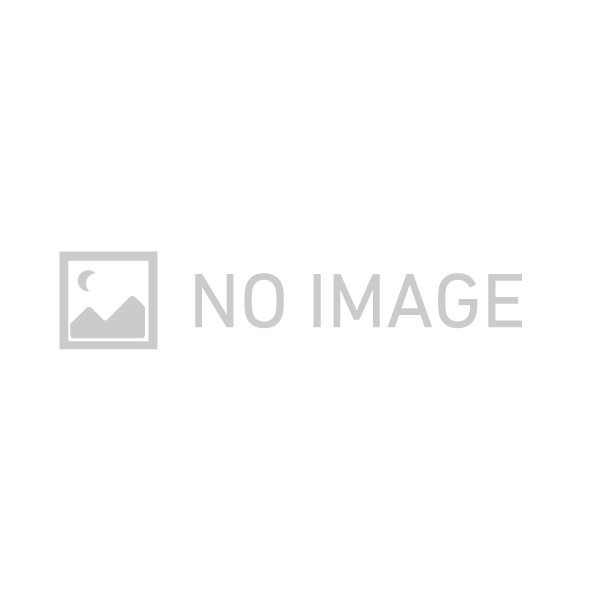哲学と宗教と科学と
以前、アメリカの大手IT企業が哲学者を採用し始めたという話を以前に書きましたが、近年 現象学の山口一郎氏が「直観の経営」や「職場の現象学」といった現象学を経営に結びつけた著作を発表され、私自身もこうした流れを大変興味深く思っています。
わたしの現象学との出会いは、30年前の学生時代に竹田青嗣氏の「現象学入門」(NHKブックス)にであった衝撃にありました。フッサールの説いた、認識というものを、すべて意識に現れる「現象」としてとらるという(映画のマトリックスのような)大胆かつ根源的な考え方に目からうろこが落ちる思いがして、なぜかとても惹かれるものを感じ、竹田氏の講演会などによく通ったことを思い出します。
こうした「現象学」というものを見直したときに、改めて経営や組織というものに哲学が入ってきているという現代の流れが腑に落ちるところがあります。竹田氏と共著も多い西研氏も、哲学とは「価値観が異なる物同士が対話によって合理的な共通理解を得る」ことと解説されていると理解していますが、例えばオフサイトミーティングを通じて企業の使命を改めて問い直すということは、まさにこうした哲学的な行為といえるような気がします。
特に「現象学」について焦点をあてれば、現象学には「本質観取」あるいは「本質直観」という重要なプロセスがあると理解しています(山口氏の著作も「直感」ではなく「直観」)。これはある物事の本質となることを前提条件なしに、物事の本質をとらえる行為ということとかなり丸めていえるのではないかと思います。その意味で、対話を通じて組織の使命や存在意義を明らかにするということは、さまざまな価値観や経験をもつものが、今までの事業のなかで何が私たちの存在としての本質であるかということの共通認識をとりだしていく行為ともいえるような気がするのです。
米国の鉄道会社がその事業ドメインを「鉄道」から「輸送」に再定義して生き残ったというのは有名は逸話ですが、これはドメインの再定義という以上に、鉄道というものののもつ本質観取的な行為といえる部分もあるかと思えます。その意味で、企業の使命を改めて対話的につくりだしていく行為には、この本質観取の原理を一部応用することで、その対話プロセスがより明確につくれるのではないかと思うのです。
哲学的な対話では、合理性があれば今まで作り上げた合意事項が見直しされることが許される(あるいはそうあらねばならない)と言えます、一方で宗教的な対話は(神の啓示に代表されるような)独善的なストーリーをよりどころとするものともいえるでしょう。その意味で、企業のビジョンは、経営者のストーリーに基づく宗教的な価値観表明であり、一方、使命の言語化プロセスは上記のような哲学的な場という要素がふくまれると整理できるのではないでしょうか。
こうした、ビジョン=宗教的ストーリー、ミッション=現象学的本質観取というとらえかたはちょっと偏っている気もしますが、改めて自分なりに整理しやすい気がしています。そして、数字に基づく科学的な管理というもの(現象学は自然科学をも包含するものでありますが)を加え、こうした科学、哲学、宗教という3つの要素が、合理性をもとめつつ、意味と価値が主体として必要な人間という集団の中にバランス良く必要とされるものではないかと思うのです。
近年は統計分析では無く、事例からの普遍法則を探るということ(質的アプローチ)が経営にもとりいれられつつありますが、そのよりどころに現象学があるともいわれるようになってきていると理解しています。気候変動や戦争など、世の中の先が見えなくなっている今日において、よりよく活きるとはどういうことかを考えることは、アテネの繁栄がおわった混迷の時代にあらわれたソクラテスの問いかけとなんら変わっていないのかも知れないと感じています。