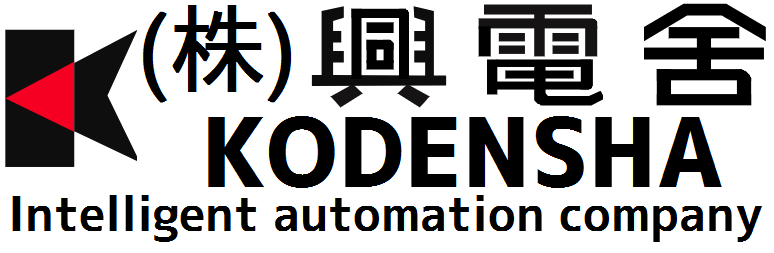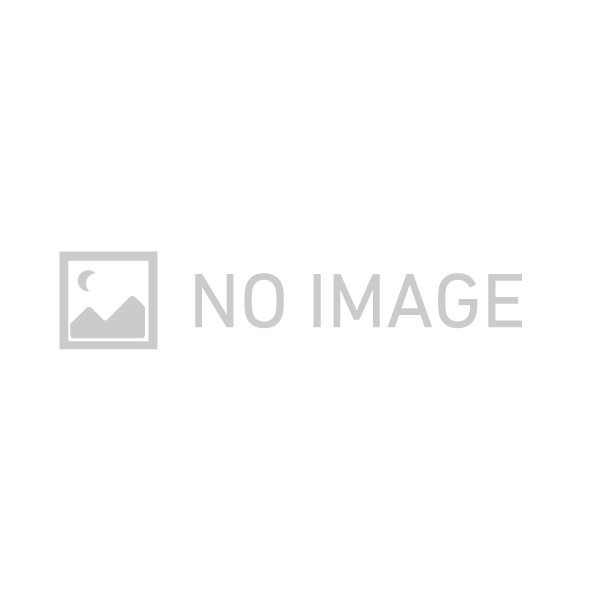脱中心化ということ:立花隆氏の生涯
度々番組の話題で恐縮だが、年末に立花隆のドキュメンタリーを見た(「見えた 何が 永遠が 〜立花隆 最後の旅 完全版〜」 NHK)。ご自身で「勉強が仕事」といわれるその飽くなき知への探求の姿勢に改めておどろかされた。が、特に印象にのこったのは、ご自身ががんに罹患した際、その治療法を調べないことを前提に、がんそのものの原理について、医学的・生物学的探求していったその姿勢である。
通常自分が病になれば、その治療法には、そもそもの探索能力が優れた氏であればこそ、当然のごとく関心をもたれるように推察する。立花氏は、がんそのものの発生が、生命の誕生や免疫といった生命維持の原理と分かちがたく結びついていることを、最新の専門家の研究にまで踏み込んで追求し、ついには生命にとって生きることそのものが死そのものである、という境地にたどりつく。ご自身の手術中に電気メスの操作を面白そうに観察するあなたは、患者なのか、医学生なのか、なにものなのか。
私が市井の知の巨人と思っている酒井穣氏は、「リーダーシップ進化論」や「自己啓発をやめて哲学をはじめよう」といった著作の中でしばしば「脱中心化」について語られる。これはもともと発達心理学者のジャン・ピアジェ考案による子供の認知の変化のプロセスで、自己中心性から脱する段階を意味する。ケン・ウィルバーも「成長とは自己中心性が減少することだ」と看破したように、大人の発達というものへの関心が深まる昨今、生涯においてこうした深い「脱中心化」が一部の人でみられることを、酒井氏はロバートキーガンの理論を(一部注意深く批判しつつ)引用している。
わたし自身は、たとえば自分の病を客観視できるような、自己中心性の枠から抜け出せることなど想像もつかず、時には自身の信念を見直そうと奮闘したり、またポジティブシンキングにはまったりしながら、思うにまかせない人生のできごとをやりくりしている。しかし立花氏の態度は、こうした自分への興味関心から離れ、真理の追求というユニバーサルなことがらに関心がうつっている。まさに酒井氏のいう「脱中心性」を体現している人物の実在に強い衝撃を覚えたのだ。
本ドキュメンタリーは、その境地にいたった背景を、ホスピスでの死にゆく患者との対話にみいだしつつ、またエーゲ海の周辺の遺跡をめぐった著作「エーゲ:永遠回帰の海」を20年かけてまとめる中で自覚した、人類の歴史の長さと奥深さに対する一人の人間の生命の短さへの達観を、そのタイトルに冠している。たまたま酒井氏が脱中心化のプロセスにおける永遠性の自覚に言及されていたのを知ったところだったので、これを体験的につかみ取った人物として、立花氏の存在そのものを再認識させていただいた。
よく世間では、「自分をみつめよ、自分をふりかえれ」、と内省が奨励される。しかし、こう考えると我欲を手放すことのハードルの高さははかりしれない。むしろ思うに任せない人生の流れというものに時にやるせなさを感じつつ、手放せない自身の限界を限界と承知しながら、その関心を外へ外へ向けていこうと試みることが、一つの拓かれた道の可能性のようにも思えるが、その道ははたして見えるのだろうか。
立花氏が、動物と人間の違いは生物学的なDNA以外に、言語というものを通して世代を超えた「遺伝情報」を保持し得ることだと言われたことも、このドキュメンタリーのハイライトであった。霊魂や死後の世界というものを否定し、自身の遺体をゴミと一緒にすてろとまで言い放った唯物論の局地に至った氏が、それでも「いのちのつながり」について永遠回帰の希望をもっていたことの重みを感慨深く、齢を刻む年のはじめに世代を超えて組織に生きる者として、感じることのできた正月となった。