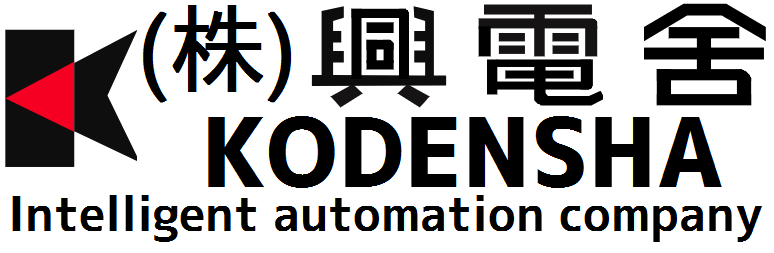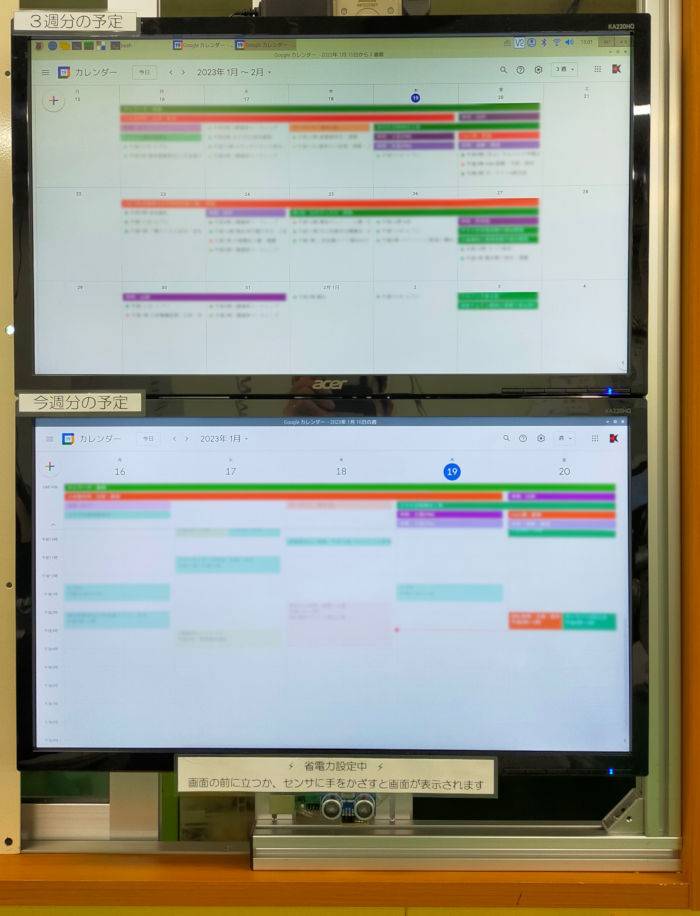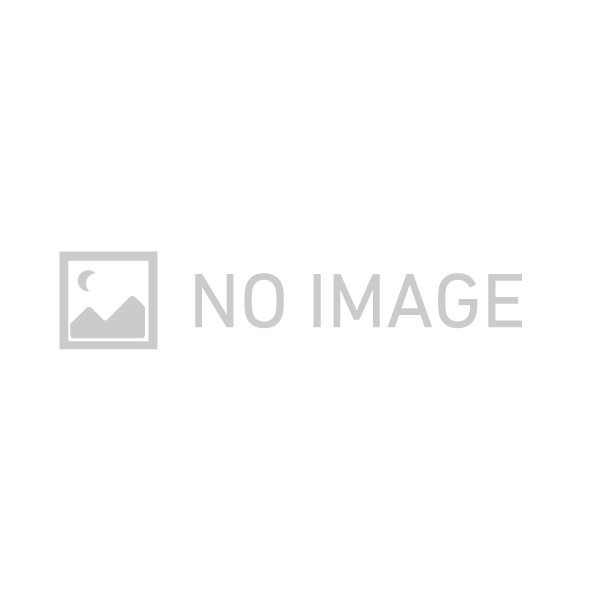生きるという宿題
昨日は映画の日であったこともあり、封切りされた「生きる-Living」を近所のシネコンでみてきた。これは黒澤明の「生きる」をかのカズオ・イシグロの脚本により、設定を当時のイギリスに置き換えたリメイク版である。派手な演技の映画がもてはやされる昨今、こうした作品は、やや敬遠されるところもあるのか、劇場はわりと空いていた。
お恥ずかしながら、私は原作の「生きる」を見ていない。ずいぶん前に「死ぬまでにしたい10のこと(My life without me)」という、同様のプロットの作品をエンターテイメントとしてみたが、黒澤の手によるブランコに載っている志村喬の映像は自分にとってあまりにも主題がストレートすぎた。
しかしながら、残された時間が意識される年齢になったのか、半ば、人生の宿題をこなすような気持ちで映画館にでかけたのだ。
映画では、主演のビル・ナイの抑制された演技にうならされた。その昔「ラブアクチュアリー」というヒュー・グラント主演のラブコメ映画で、素っ頓狂な歌手の役をやっていたが、20年経ってこうした奥行きのある演技をみると、役者としての振り幅の大きさに改めて感じ入るものがある。
そして、主人公に生き方のモデルをしめす女性(マーガレット)の役で登場する、エイミー・ルー・ウッドも、ビル・ナイと対称的な、奔放かつ表情豊かな演技ぶりに大いに好感がもてた。
オリジナルよりもあっさりと軽やかに描かれているという映画評もあるようだが、それでも、本当の意味で生きているか、という作品からの問いに、日々あくせく暮らしている身としては深く考えさせられる。
自分自身も、振り返ると活き活きと生きていなかったと思われる局面が人生の節々であった。
最初に思い出されるのが、学生時代のことだ。周りの仲間が将来を夢見て、進学に向けて一生懸命勉強をしていた。そうしたときに(狭い了見なのだが)自分は、親の仕事を引き継ぐことが、その期待に応える唯一の道だと勝手に思い込んでいた。これは言い訳なのだが、どうせ道はきまっているのだと、なんだか受験勉強に意味を見いだせず、学校をさぼって山手線を日長ぐるぐると回っていたことを思い出す。
その後も、あくせく仕事をするなかで、時には顔面蒼白で生気をうしなっていたこともあった。若いときはマーガレットのように、愉しみをみいだせていたわけでもなかった。とにかく日々が必死でしかなかった。そしてその後決定的に自分を失う経験をするのだが、これはまだ良く整理できず言葉にできない。
ひとついえるのは、若いときには人生が果てしなく続く永遠のものと感じられたということ。そして、年を重ねる中で、失ってはじめてその価値に気がつくということが、たくさんあったことに愕然とすることが多くなった。
死を目前にして、生きる喜びをとりもどした主人公もすばらしい。しかし、主人公の生き様に学びながらも、我が身を守るために、繰り返される日常にどっていくその他の登場人物もまた真実であると感じる。
以前、齢90才を越えた地元の創業者の方のお葬式で、亡くなる何年か前にとったご自身の人生を振り返ったインタビュービデオを拝見した。そのときは、感銘をうけつつなんとまあ用意周到なことかと思ったものだ。こうした自身の死を準備できる方はまれだろう。実際父も母も、突然の病の宣告からは、それこそ病魔と闘うことに精一杯で最期を迎えたように思う。特に母などは、遺品の行き先の一つ一つまで自分で名札をつけて死の仕度をしていて、経理をしていた生前の仕事ぶりを思わせる。が、亡くなった後に出てきたパスポートに一つも出国の判子が押していなかったのを見たとき、なんともやるせない気持ちになった物だった。
もろもろ考えて澱のように残るのは、この宿題には答えがないな、ということと、それでも早く宿題を解かなくてはいけないという焦燥感である。焦って生きる意味を考えても答えは出ないかも知れない、しかし、人生が様々な体験をする旅であるとすれば、それでも今日、自らの意思で向き合える事柄があるということは、それがたとえどんな事柄であろうとも、案外と幸せなことなのだろう。
さあ、これからどこに向かって旅をしようか。